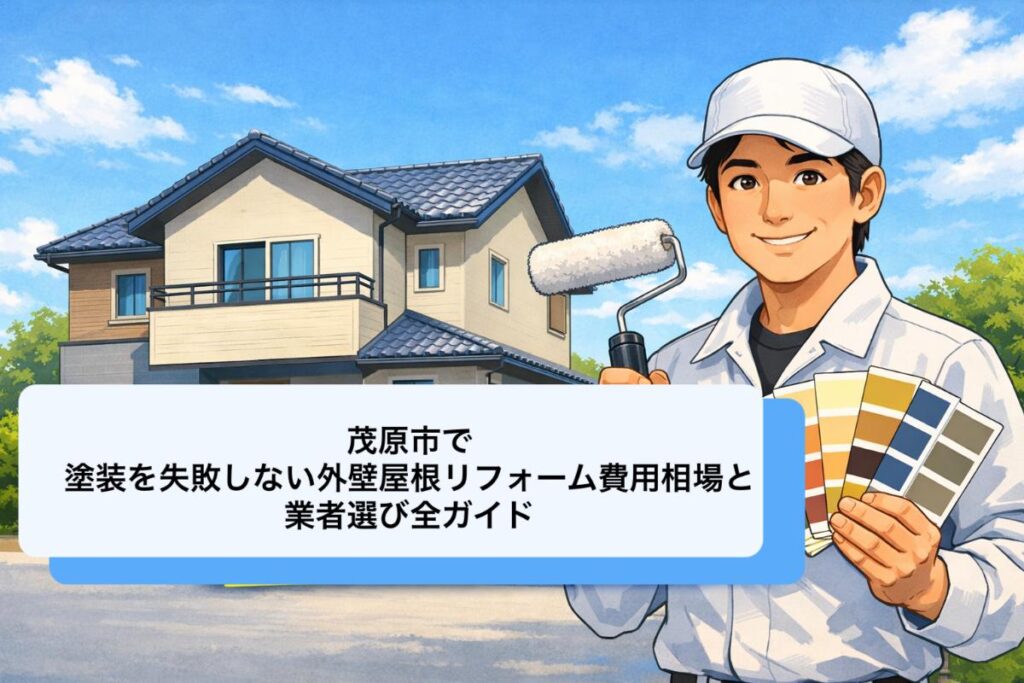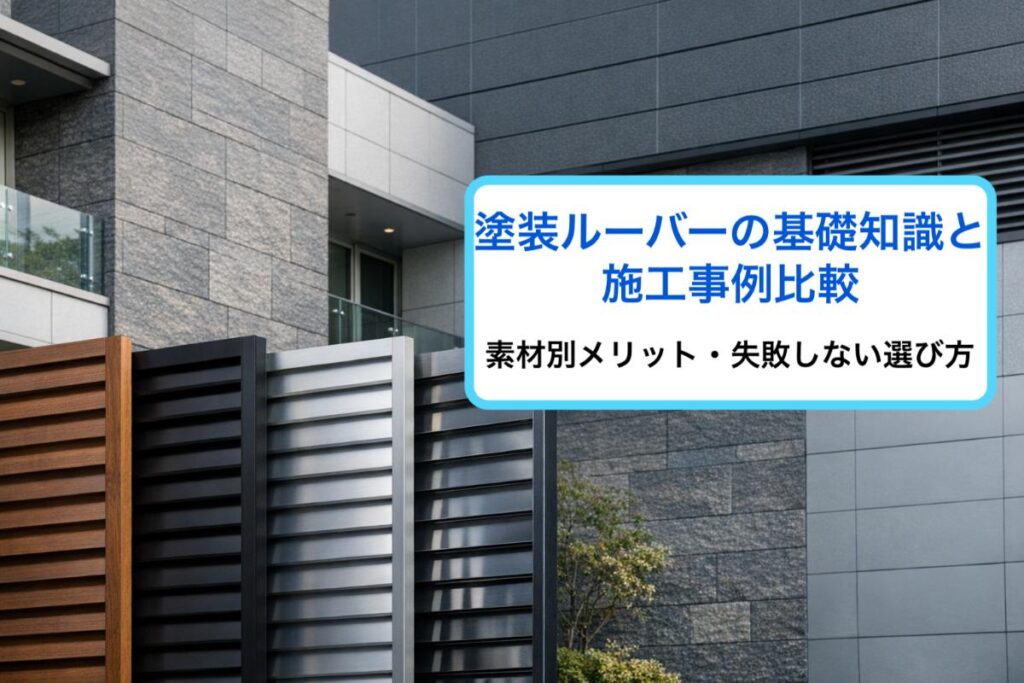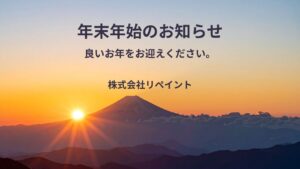市原市に外壁塗装の助成金はあるの?市原市の補助金について解説いたします!


住宅・建築関係(リフォーム等)の補助金について
まずは千葉県市原市について詳しくご説明いたします!
市原市の補助金について解説いたします!
市原市では、住宅や建築物等に関連して、補助制度・支援制度がございます。
※令和7年4月現在での情報です。
※市原市では、外壁等の塗装の補助はおこなっておりません。
市原市がけ地近接住宅移転事業補助金制度について
住宅に居住する者が行うがけ地近接危険住宅移転事業に要する費用について、補助金を交付する制度です。
危険住宅に居住する者が行う、危険住宅の除去や新たな住宅の建設又は購入に要する費用に係る借入金利子に対して補助する制度です。
け地の崩壊等による住民の生命に対する危険を防止することを目的としています。
1.補助対象の要件
・市内の「危険住宅」に居住している者で、市税を滞納していない者。
※「危険住宅」とは、建築基準法施行条例第4条に規定する基準に適合しない、昭和47年10月19日以前に建築された住宅をいう。ただし、昭和47年10月20日以後において、増築、改築、大規模な修繕又は大規模な模様替の工事を行った住宅は対象外となる。
★建築基準法施行条例第4条(がけ付近の建築物の敷地等)
傾斜度30度を超え、高さ2メートルを超えるがけ地で、
・がけ上では、がけ地の下端からがけ地の高さの1.5倍の範囲内
・がけ下では、がけ地の上端からがけ地の高さの2倍の範囲内 が危険区域
★移転事業(申請から交付決定を受け、移転先への住宅建設(購入)と危険住宅の除却をし、実績報告をするまで。)を年度内(2月末日)に完了させることが条件となります。
2.補助金の額
(1)危険住宅除却事業
危険住宅の移転を行う者に対して危険住宅の除却等に要する費用を交付する事業。
・ 危険住宅除却等に要する経費に相当する額。1戸当たり728千円を限度とする。
(2)建物建設(購入)事業
危険住宅の移転を行う者に対して、危険住宅に代わる住宅の建設又は購入をするために要する資金を金融機関から借入れた場合に、当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする)に相当する額。1戸当たり3,560千円(建物2,560千円、土地800千円、敷地造成200千円)を限度とする。
都市部宅地課
電話0436-23-9839
【緑化助成金】自宅に生垣を設置しませんか?|生垣設置奨励補助金
緑化の推進とブロック塀などの倒壊による災害の防止のために、住宅用地への生け垣の設置に補助金を交付する制度です。
概要
市原市では、緑化の推進とブロック塀の倒壊による災害防止のため、住宅用地に生垣を新たに設置する方に補助金を交付しています。
上総更級公園の公園センター前(西側)に、生垣を設置しておりますので、参考にご覧ください。
※必ず生垣を設置する前に申請をしてください。
補助金の金額
生垣の長さ1mにつき2,000円を、最大25mまで長さに応じて補助します。
生垣を設置するために、ブロック塀などを撤去する場合は、1mにつき2,500円を上記の金額に加算し、最大20mまで長さに応じて補助します。
補助金の対象になる主な条件
住宅用地への生垣の新設であること。
生垣の総延長が5m以上であること。
生垣を設置する位置が土地境界線上であること。
樹木の本数が1mにつき2本以上であること。
外部から眺望できる樹木の高さが概ね50cm以上であること。
樹木の種類が市原市が推奨する健全な樹木であること。
生垣を支柱で固定していること。
過去に同じ土地で生垣設置奨励補助金の交付を受けていないこと。
ブロック塀などを撤去する場合の補助対象条件
生垣を設置する場所の塀の高さが100cm以上であること。
撤去する塀の材質がコンクリート・レンガ・石・ブロックであること。
着工前の現場確認時に塀を撤去していないこと。
※危険ブロック塀等の安全対策事業のご案内は下記詳細リンクをご確認ください。
推奨樹種および補助対象外樹種
高木
1 イヌマキ 9 ツバキ
2 イヌツゲ 10 ニッコウヒバ
3 カナメモチ 11 キャラ
4 ネズミモチ 12 サンゴジュ
5 ウバメガシ 13 マサキ
6 ドウダンツツジ 14 ムクゲ
7 ピラサンカ 15 トキワマンサク
8 サザンカ 16 セイヨウイボタ
低木
1 ツツジ(類) 8 ツゲ(類)
2 ジンチョウゲ 9 アジサイ
3 センリョウ 10 コデマリ
4 ナワシログミ 11 ボケ
5 ハクチョウゲ 12 アベリア
6 マンリョウ 13 ボックスウッド
7 金芽ツゲ
上記以外の樹種の設置を希望する場合は、事前にご相談ください。
なお、次の樹種は補助対象外ですので、注意してください。
カイヅカイブキ
キョウチクトウ
タケ類
バラなどのツル植物
食用を目的とする樹種
生垣設置後に守っていただくこと
樹木の良好な生育を保つため、病害虫の防除、剪定、施肥等の必要な措置を行うこと。
交通及び他人の土地の障害となる枝葉の整枝を行うこと。
植栽から5年間は樹木の伐採や移植は行わないこと。
枯木はただちに補植し、現状を維持すること。
申請から交付までの流れ
1.申請書の提出
必ず、生垣を設置する前に申請してください。生垣設置後の申請は補助金の対象となりませんのでご注意ください。なお、申請の際は、申請者の印鑑、交付金の振込口座番号が確認できるものをご持参ください。
提出書類は次のとおりです。
・市原市生垣設置奨励補助金交付申請書
・生垣設置計画書
2.着工前現地確認
市職員が生垣設置予定箇所を確認します。
3.補助金交付決定通知の発送
4.着工
市原市からの連絡後、生垣の設置工事に着手してください。
5.工事完了届の提出
工事完了後、公園緑地課までご連絡ください。
提出書類は次のとおりです。
・市原市生垣設置工事完了届
6.完了後現地確認
市職員が生垣設置箇所を確認します。
7.補助金確定通知書の発送
8.補助金の請求
提出書類は次のとおりです。
・市原市生垣設置奨励補助金交付請求書
9.補助金の交付
請求書提出後、1ヶ月ほどで指定された口座へ振り込まれます。
都市部公園緑地課
電話0436-23-9842
合併処理浄化槽の補助金
市では、未処理の生活雑排水が公共用水域へ放流されることによる水質汚濁防止を目的に、合併処理浄化槽を設置する人に対して予算の範囲内で補助金を交付します。
要件や申請方法など、詳細については市原市役所にお問合せください。
令和7年度合併処理浄化槽設置事業補助金の予算状況
予算残額(令和7年9月30日現在)
22,238千円
補助金の申請受付につきましては、予算に達した時点で受付終了となります。
受付終了は、ウェブページ上でお知らせします。
補助を受ける条件
次の(1)から(4)のいずれにも該当する場合に限り、補助金を交付します。
(1)市原市内において、住宅に10人槽以下の合併処理浄化槽を浄化槽法、その他関係法令に従って設置しようとする個人であること。
(2)合併処理浄化槽の設置場所が、市原市汚水処理整備構想に定める公共下水道事業区域(ただし、事業実施が当分の間見込めない区域としてあらかじめ別に定める区域を除く。)や農業集落排水事業採択区域でないこと。
(3)市原市の市税に滞納がないこと。
(4)年度内(2月末日)までに工事が完了すること。
注意点:補助金申請前に工事を着工してしまうと、補助金が受けられなくなります。ご注意ください。
補助金の申請方法
合併処理浄化槽設置補助金の申請には、申請書類が必要となります。
詳しくは市原市合併処理浄化槽設置事業補助金申請の手引きをご確認ください。
浄化槽法第10条に規定する浄化槽の保守点検及び清掃の実施を誓約するための書類です。
合併処理浄化槽設置事業補助金の交付申請の際に、場合によっては必要となる書類です。
環境部資源循環推進課
電話0436-23-9857
令和7年度「市原市住宅用設備等脱炭素化促進補助金」のご案内
家庭における地球温暖化対策推進のため、脱炭素化及び電力の強靭化に資する住宅用設備等を導入した市民の方に、補助金を交付する制度です。太陽光発電システム(※新築は対象外)、家庭用燃料電池システム(エネファーム)、定置用リチウムイオン蓄電システム、窓の断熱改修(※新築は対象外) 、太陽熱利用システム 、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、Ⅴ2H充放電設備、集合住宅用充電設備(※新築は対象外)、住民の合意形成のための資料、などの補助メニューがあります。
概要
家庭における地球温暖化対策推進のため、脱炭素化及び電力の強靭化に資する住宅用設備等を導入した市民の方に、補助金を交付します。
申請受付期間
令和7年4月1日(火)~令和8年2月27日(金)
※令和7年4月1日以降に着工し完了したものを、先着順に受付し、補助可能額が無くなった時点で受付を終了します。
※補助可能額が無くなる日の申請分については、抽選により受付順を決定します。
補助金予算残額(令和7年10月14日現在)
予算額
50,890,000円
補助可能額(太陽光発電システム)
6,558,000円
補助可能額(太陽光発電システム以外)
22,707,000円
補助対象設備・補助金の額
太陽光発電システム(※新築は対象外)
補助金の額:設置する太陽電池の最大出力(小数点以下第3位を四捨五入)に1kWあたり2万円を乗じて得た額(上限9万円)
太陽電池を利用して電気を発生させるための設備及びこれに付属する設備であって、設置された住宅において電気が消費され、連系された低圧配電線に余剰の電気が逆流されるもののうち、次の要件を満たすもの。
【次のいずれかの設備が導入されていることが必要です。】
・エネルギー管理システム(HEMS)
・定置用リチウムイオン蓄電システム
・電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車及びV2H充放電設備
1.住宅用の低圧配電線と逆潮流有りで連系するものであること。
2.太陽電池の出力状況等により、起動及び停止等に関して全自動運転を行うものであること。
3.太陽電池モジュールが、次のいずれかの規格等に適合していること。
ア 国際電気標準会議の規格又は日本産業規格に適合しているものであること。
イ 一般財団法人電気安全環境研究所の認証を受けているものであること。
ウ 一般社団法人太陽光発電協会JPEA代行申請センターにおいて設備認定に係る型式登録がされているものであること。
4.対象設備を構成する太陽電池の公称最大出力又はパワーコンディショナーの定格出力のいずれか小さい方(複数のパワーコンディショナーを設置する場合、系列ごとに当該値を合計した数値)が10キロワット未満であること。なお、既存設備の出力を増加する目的で設備を設置する場合は既存設備分を含めた増設後の設備が上記の要件を満たすこと。
家庭用燃料電池システム(エネファーム)
補助金の額:補助対象経費の額(上限10万円)
燃料電池ユニット、貯湯ユニット等から構成され、都市ガス、LPガスなどから燃料となる水素を取り出して空気中の酸素と反応させて発電し、発電時の排熱を給湯等に利用できるもののうち、次の要件を満たすもの。
1.一般社団法人燃料電池普及促進協会の機器登録を受けているものであること。
2.停電時自立運転機能を有するものであること。
※過去に補助を受けた補助対象設備を交換又は増設する場合は、取得した日から6年を経過していること。
定置用リチウムイオン蓄電システム
補助金の額:補助対象経費の額(上限7万円)
リチウムイオン蓄電池部(リチウムイオンの酸化及び還元で電気的にエネルギーを供給する蓄電池をいう。)、インバータ等の電力変換装置を備え、再生可能エネルギーにより発電した電力又は夜間電力などを繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時など必要に応じて電気を活用することができるもののうち、国が令和5年度以降に実施する補助事業における補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されているもの。
※リース契約で購入した場合、県の補助金との併用はできません。
※過去に補助を受けた補助対象設備を交換又は増設する場合は、取得した日から6年を経過していること。
窓の断熱改修(※新築は対象外)
補助金の額:補助対象経費の2分の1の額(上限16万円)
既存住宅に設置されている窓を、断熱性能が高い窓へ改修する(内窓の設置を含む。)もののうち、次の要件を満たすもの。
1.国が令和5年度以降に実施する補助事業の補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブ又は公益財団法人北海道環境財団により登録されているものであること。
2.1室(壁、ドア、障子、襖等で仕切られている空間)単位で外気に接する全ての窓の断熱化をするものであること。
※マンション管理組合による改修においても、補助金の交付対象となります。申請を検討されている場合は、事前にご相談をお願いいたします。
電気自動車
※住宅に太陽光発電設備が設置されているまたは併せて設置し、発電した電気を電気自動車等に充電できることが必要です。
補助金の額:補助対象経費の額(上限30万円(Ⅴ2H充放電設備を併設する場合)又は上限20万円(併設しない場合))
電池によって駆動される電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車検査証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう。)で、自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が「電気」、用途が「乗用」、自家用・事業用の別が「自家用」と記載されている4輪のもののうち、次の要件を満たすもの。
※住宅用太陽光発電設備が既に設置されている又は併せて設置した場合に限る。
1.申請者が補助金の交付を受けるに当たり、新車として新たに購入したもの(中古の輸入車の初度登録車を除く。)であること。
2.自動車検査証の使用の本拠の位置が、市内の住所であること。
3.自動車検査証の登録年月日又は交付年月日が、補助金の交付を受ける年度内の日付であること。
4.国が令和5年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされている電気自動車であること。
プラグインハイブリッド自動車
※住宅に太陽光発電設備が設置されているまたは併せて設置し、発電した電気を電気自動車等に充電できることが必要です。
補助金の額:補助対象経費の額(上限30万円(Ⅴ2H充放電設備を併設する場合)又は上限20万円(併設しない場合))
電池によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ、外部からの充電が可能な自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車検査証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう。)で、自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が「ガソリン・電気」または「軽油・電気」、用途が「乗用」、自家用・事業用の別が「自家用」と記載されている4輪のもののうち、次の要件を満たすもの。
※住宅用太陽光発電設備が既に設置されている又は併せて設置した場合に限る。
1.申請者が補助金の交付を受けるに当たり、新車として新たに購入したもの(中古の輸入車の初度登録車を除く。)であること。
2.自動車検査証の使用の本拠の位置が、市内の住所であること。
3.自動車検査証の登録年月日又は交付年月日が、補助金の交付を受ける年度内の日付であること。
4.国が令和5年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているプラグインハイブリッド自動車であること。
Ⅴ2H充放電設備
補助金の額:補助対象経費の5分の1の額(上限50万円)
電気自動車等と住宅の間で相互に電力を供給できる設備のうち、国が令和5年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているもの。
※住宅用太陽光発電設備が既に設置されている又は併せて設置した場合に限る。かつ、電気自動車が既に導入されている又は併せて導入した場合に限る。
集合住宅用充電設備(※新築は対象外)
補助金の額
(1)住民のみ充電設備を利用可能な場合
設備本体の購入費に係る国の補助金の補助金額に3分の1を乗じた額(1基(口)あたり上限50万円)
(2)住民以外も充電設備を利用可能な場合
設備本体の購入費に係る国の補助金の補助金額に3分の2を乗じた額(1基(口)あたり上限100万円)
集合住宅の管理者等が電気自動車等に充電するために導入する以下の設備のうち、国が令和5年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているもの。
1.急速充電設備
2.普通充電設備
3.蓄電池付急速充電設備
4.充電用コンセント
5.充電用コンセントスタンド
住民の合意形成のための資料
補助金の額:補助対象経費の額(上限15万円)
マンション管理組合が住民の合意形成のために作成する充電設備の導入に係る説明資料(充電設備の設置場所見取図、平面図、電気系統図、配線ルート図及び住民の費用負担のシミュレーション等)で、当該資料を使用することにより、マンション管理組合の総会で集合住宅用充電設備の導入についての議論が行われるもの。
※書類が全て揃っていない、記載事項に不備がある等の場合、受理することができませんのでご注意ください。書類が全て揃った時点で受理となります。「申請書類チェックシート」及び「Q&A」により必要書類の確認をし、提出してください。
令和7年度申請様式
市原市住宅用設備等脱炭素化促進補助金交付申請書(第1号様式)
市原市住宅用設備等脱炭素化促進補助金交付請求書(第5号様式)
市原市住宅用設備等脱炭素化促進補助金処分承認申請書(第6号様式)
補助金の額の計算
1. 補助金は、補助対象設備の種類ごとに、一つの住宅に1回に限り交付します。ただし、過去に補助金の交付を受けた方と異なる世帯を構成する方が、補助対象設備を導入した場合は補助対象となります。
※家庭用燃料電池システム及び定置用リチウムイオン蓄電システムにおいては、過去に補助を受けた補助対象設備について、取得した日から起算して6年を経過し、これを交換又は増設する場合はこの限りではありません。
なお、電気自動車・プラグインハイブリッド自動車にあっては、導入する住宅において申請者ひとりにつき1回交付することができます。
2. 補助対象経費は、主に、設備本体・付属品の購入費及び工事費となります。電気自動車・プラグインハイブリッド自動車・V2H充放電設備にあたっては、本体の購入費のみとなります。
詳しくは、「令和7年度「市原市住宅用設備等脱炭素化促進補助金」のご案内」をご確認ください。
3. 補助対象経費において、消費税及び地方消費税相当額は控除するものとし、導入費等に国その他の団体から補助金を充当する場合は、さらに当該補助金の額を控除した額となります。
4. 補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額となります。
申請手続きの流れ
交付の申請
設置工事完了後、令和8年2月27日(金)までに、「市原市住宅用設備等脱炭素化促進補助金交付申請書(第1号様式)」に必要書類を添付し、市原市役所第2庁舎5階「環境管理課」へ持参又は郵送により、提出してください。
※各支所での受付は行っておりません。
※申請書等は市ホームページからダウンロードできます。
※申請日は書類を受付した日付になります。
※FAX・Eメール・データ持込みでの申請は受付けません
交付の決定
市から交付決定した方へ、申請された日から約1か月で「交付決定通知書」を送付します。(補助要件を満たしていない方へは、「不交付決定通知書」を送付します。)
補助金の交付処理
交付決定を受けた方は、決定通知を受けた日から起算して15日を経過する日までに、「市原市住宅用設備等脱炭素化促進補助金交付請求書(第5号様式)」をご提出ください。
交付請求書を基に、口座振込を行います。
なお、交付請求書は、申請書類と併せて提出することも可能です。
提出する際は、銀行名や支店名等に間違いがないかご確認ください。
申請から補助金が交付されるまで、約2か月です。
環境部環境管理課
電話0436-23-9867
公共下水道接続に係る補助金・利子補給
下水道供用開始後、3年以内に公共下水道に接続していただくために、既存のし尿浄化槽や汲取便所の改造にかかる費用の一部を助成、または改造にかかる借入金の支払利息の一部を補給する制度です。
市では、公共下水道へ速やかに接続していただくために補助金と利子補給制度を設けています。(※併用はできません。また、新築家屋・事務所などについては対象外です。)
1.補助金制度
くみ取便所・し尿浄化槽を廃止し、公共下水道に接続した場合が対象となります。
- 条件金額公共下水道の供用開始日から、1年以内に工事を完了した場合
1棟につき3万円公共下水道の供用開始日から、1年を超え3年以内に工事を完了した場合
1棟につき1万円
2.利子補給制度
下水道の宅内工事をするための工事資金を市の指定金融機関から借入れた場合、返済時に生じる利子を補給する制度です。
なお、対象となる要件は次の通りです。
1.利子補給の対象となる限度額
- くみ取便所を水洗便所に改造して公共下水道に接続する工事---1便槽につき45万円
- し尿浄化槽を廃止して公共下水道に接続する工事---浄化槽1基につき35万円
2.年利11.7%以内
3.利子補給期間は36ケ月(3年)以内
4.市原市水洗便所改造資金利子補給指定金融機関
- 千葉銀行
- 京葉銀行
- 千葉信用金庫
- 木更津信用金庫
上下水道部下水道管理課
電話0436-23-9043
狭あい道路後退用地整備事業
幅員4m未満の市道に接する土地において、建築行為を行う場合や道路の拡幅整備を希望する場合に、後退用地やすみ切り用地を市に寄付していただき、市が拡幅整備を行う事業です。この事業に際し、後退用地及びすみ切り用地にある門柱・塀・擁壁・樹木・生垣等の除却費用の一部を助成します。また、すみ切り用地を寄付していただいた場合には奨励金を交付する事業です。
私たちの身近にある道路は、住みやすい住環境を確保し、災害時の安全性を高める上で重要な役割を担っています。
しかし、市内には4mに満たない道路(狭あい道路)がたくさんあります。
このような狭あい道路では、安全な通行や日照・通風などの生活環境に問題のあるもの、災害時の避難の妨げになるもの、消火活動・救急活動に支障をきたすものなど、さまざまな問題を抱えています。
そこで、市原市では道路の幅員を4m確保することを目的に「狭あい道路後退用地整備事業」を平成15年4月よりスタートさせております。
この事業は、市民の皆さんに道路用地を提供していただき、市が道路整備を行うことにより、安全で良好な生活環境を実現しようとするものです。御理解と御協力をお願いいたします。
狭あい道路整備のメリット
緊急車両の通行がスムーズになる
安全な通行幅の確保ができる
日照、通風等 生活環境の改善ができる
建築に伴うセットバック用地の維持管理の負担が減る
整備促進地区について
整備促進地区とは、まちづくり構想及び地区計画に基づいて狭あい道路の整備を進める地区として位置づけられた地区で、下記のとおり指定されています
郡本・藤井・門前・市原地区(平成22年4月から)
古市場地区(平成30年4月から)
事業の対象について
| 対象となる道路 | 市街化区域内にある幅員4m未満の市道又は市道認定外道路(市が底地を所有しているものに限る。) |
|---|---|
| 対象となる後退用地 | 道路の拡幅整備のために後退する用地 |
| 対象となるすみ切り用地 | 道路が他の道路と交わる角地に設ける用地 |
※事業の対象区域は原則として市街化区域ですが、市街化調整区域においても対象となる場合がありますので、ご相談ください。
助成金の交付について
後退用地及びすみ切り用地内にある物件(門柱、塀、擁壁、樹木、生垣等)の除却に助成金を交付します。(申請前に除却したものは対象外となります)
整備促進地区においては、除却後の移設又は新設にも助成金を交付します。
助成金は損失補償算定標準書または国土交通省土木工事標準積算基準書に基づき算定します。
1.【撤去】コンクリートブロック塀
→損失補償算定標準書に基づいた額(高さに応じて変動)×延長=助成金交付額
2.【新設】コンクリートブロック塀及びフェンス(新設は整備促進地区のみ対象)
→損失補償算定標準書に基づいた額(高さに応じて変動)×延長=助成金交付額
奨励金の交付について
すみ切り用地を寄附していただいたときは、奨励金を交付します。奨励金の額は、すみ切り用地面積の固定資産税評価額に相当する額となります。
市が行う整備等について
後退用地やすみ切り用地を寄付していただけるときに、道路の境界が確定していないときは、寄附者との協議の上、境界を確定するとともに、用地の測量・分筆・所有権移転登記を行います。
その後、現況道路の整備状況に応じて整備を行います。
土木部土木管理課
電話0436-23-9831
高齢者の自立を促し、介護に適した環境づくりをするために、住宅を改造する費用について助成する事業です。
対象者
次の全ての要件を満たす方
- 市内に居住していて、満65歳以上で介護保険法による要介護3~5の認定を受けている方
- 同居している家族のうち、最多収入者の当該年度分の市民税(4月から6月までに申請する場合は前年度分の市民税)の所得割額が16万円未満である方
- 同居している家族及び申請者の全員が市税を滞納していないこと
対象となる工事
- 玄関、台所、廊下、居室等の改造のうち、介護保険法に定める住宅改修の種類を除く工事
- 簡易移し替え機、便座昇降機、風呂昇降機、段差解消機、階段昇降機の設置のうち、介護保険法に定める住宅改修の種類を除く工事
注記1:対象者の身体状況や介護状況と照らし合わせ、必要な工事のみが助成の対象となります。
注記2:住宅の新築、全面改築または増築に伴って行われる工事や助成の申請手続き前に着手または完了している工事は助成対象外となります。
助成金額
助成対象工事に要する費用の2分の1(1,000円未満の端数は切捨て)ですが、限度額があります。
助成上限額は、同居している家族及び申請者の全員が市民税非課税の場合は50万円、その他の場合は30万円です。
助成金は、工事が完了して市が完成確認した後に、申請者指定の金融機関にお振込みします。
申請に必要なもの
助成申請時
市原市重度障害者及び高齢者住宅改造費助成金交付申請書、工事見積書(改造を行う業者が作成した改造箇所及びその経費を明らかにしたもの)、工事箇所図面、工事前の写真、工程表、同居の家族を含む全員分の市民税課税証明書又は非課税証明書(注記1)
備考1:申請者や同居家族の所有でない住宅の場合は、住宅の所有者又は管理者からの住宅改造承諾書を併せてご提出ください。
注記1:市民税の課税状況について市長が確認する同意書の提出があれば、税証明の提出は不要です。
市原市重度障害者及び高齢者住宅改造費助成金交付申請書(PDF:70KB)
工事完了後
市原市重度障害者及び高齢者住宅改造費助成事業完了報告書、市原市重度障害者及び高齢者住宅改造費助成金交付請求書、工事後の写真、領収書の写し
注記1:領収書は原本を確認後、写しを提出していただきます。
市原市重度障害者及び高齢者住宅改造費助成事業完了報告書(PDF:59KB)
市原市重度障害者及び高齢者住宅改造費助成金交付請求書(PDF:61KB)
保健福祉部高齢者支援課
電話0436-23-9873
重度障がい者の住宅改造費の助成
重度障がい者またはその同居の家族が住宅を障がい者に適するように改造するために要する費用及び指定機器の設置費用を助成する事業です。
重度障がい者の住宅改造費の助成
重度障がい者が、住宅を障がい者に適するように改造するために要する費用を助成します。
(ア)対象者
・65歳未満で身体障害者手帳の等級が、下肢、体幹または視覚障害の1級・2級の方
(イ)助成内容
・工事に要する費用の2分の1を補助します。ただし、30万円 (非課税世帯は50万円) を限度とします。
(ウ)条件等
・同居の家族のうち最多収入者の市民税所得割額が16万円未満であること。
・市税の滞納がないこと。
・新築、全面改築または増築により行われる改造、及び申請以前に着手または完了しているものは、補助対象になりません。
※事前にお問合せの上、申請願います。
保健福祉部障がい者支援課
電話0436-23-9815
省エネ改修をした住宅に係る固定資産税の減額措置を受けたい
一定要件を満たした省エネ改修を行った住宅については、工事完了後3か月以内に申告した場合、当該工事完了日の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分の固定資産税を減額する措置です。
一定要件を満たした省エネ改修を行った住宅については、工事完了後3か月以内に申告した場合、当該工事完了日の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分の固定資産税の3分の1が減額されます。(1戸当たり住居部分の床面積120平方メートル相当分を限度とする。)
| 手続きの時期 | 改修工事完了後3か月以内。ただし、改修工事は令和4年4月1日から令和8年3月31日までに完了したものでなくてはなりません。 |
|---|---|
| 手続き可能な方 | 納税義務者 |
| 代理人による手続き | 可 |
| 手続き方法 | 改修工事完了後3か月以内に固定資産税課窓口で申告してください。 (申告書については下部よりダウンロード可) |
| 必要書類 | 省エネの改修に伴う固定資産税減額申告書住民票の写し(ただし、市原市に住民登録のある納税義務者は、現住所を市原市が確認することについて申告書で同意した場合は不要。)省エネ改修工事に係る明細書の写し(当該改修工事の内容及び費用の確認ができるもの)省エネ改修工事の領収書の写し(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が発行)改修工事の費用に充てるために交付された補助金等がわかるものの写し(令和4年4月1日から令和8年3月31日までに改修工事が行われ、補助金等が交付されている場合のみ提出)長期優良住宅認定通知書の写し(認定長期優良住宅に該当することとなった住宅のみ。ただし、既に減額の適用を受けたことがある場合を除く。) |
| その他お持ちいただくもの | 特にありません。 |
| 手続きにかかる費用 | 無料です。 |
| 手続き後にお渡しするもの | 特にありません。 |
| 所要時間の目安 | 10分程度 |
| 注意事項 | 対象となる住宅・平成26年4月1日以前に建築された住宅(注釈1、2)。 注釈1:平成28年4月1日以降の改修工事については、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅。 注釈2:併用住宅は、住居部分が全体の床面積の2分の1以上であること、貸家住宅は賃貸部分を除く。 対象となる改修工事現行の省エネ基準に合致する下記工事を行ったもの(注釈1)で、改修工事費の(補助金等を除く)自己負担額が60万円(注釈2)を超えるもの。 ・窓の断熱性又は日射遮へい性を高める改修工事(複層ガラス化、二重サッシ化などでで外気と接する部分のもの) ・天井や屋根の断熱性を高める改修工事(天井裏の断熱などで外気と接する部分のもの) ・壁の断熱性を高める改修工事(断熱材の施工などで外気と接する部分のもの) ・床の断熱性を高める改修工事(床下の断熱などで外気と接する部分のもの) 注釈1:窓の断熱性又は日射遮蔽性を高める改修工事については必須になります。 注釈2:断熱改修に係る工事費が50万円以上であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、 太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円以上が対象になります。 その他の減額措置との併用・バリアフリー改修に伴う減額措置との併用は可能です。 ・耐震改修に伴う減額措置、長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る減額措置との併用はできません。 ・省エネ改修に伴う減額措置は、同一家屋につき1回のみです。 |
住宅の省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書(PDF:141KB)
住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置について(PDF:134KB)
財政部固定資産税課
電話0436-23-9812
バリアフリー改修をした住宅に係る固定資産税の減額措置を受けたい
一定要件を満たしたバリアフリー改修を行った住宅については、工事完了後3か月以内に申告した場合、当該工事完了日の翌年の1月1日を賦課期日とした年度分の固定資産税を減額する措置です。
一定要件を満たしたバリアフリー改修を行った住宅については、工事完了後3か月以内に申告した場合、当該工事完了日の翌年の1月1日を賦課期日とした年度分の固定資産税の3分の1が減額されます。(1戸当たり住居部分の床面積100平方メートル相当分を限度とする。)
| 手続きの時期 | 改修工事完了後3か月以内。ただし、改修工事は平成28年4月1日から令和8年3月31日までに完了したものでなくてはなりません。 |
|---|---|
| 手続き可能な方 | 納税義務者 |
| 代理人による手続き | 可 |
| 手続き方法 | 改修工事完了後3か月以内に固定資産税課窓口で申告してください。 (申告書については下部よりダウンロード可) |
| 必要書類 | 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書バリアフリー改修工事に係る明細書の写し(当該改修工事の内容及び費用の確認ができるもの)バリアフリー改修工事箇所の写真(改修前後のもの)バリアフリー改修工事の領収証の写し(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)バリアフリー改修工事の費用に充てるために交付された補助金等がわかるものの写し(補助金等が交付されている場合のみ提出)下記のうちいずれか一点 ・65歳以上の高齢者:住民票の写し ・要介護認定及び要支援認定者:介護保険の被保険者証の写し ・障がい者認定を受けている方:身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等の写し |
| その他お持ちいただくもの | 特にありません。 |
| 手続きにかかる費用 | 無料です。 |
| 手続き後にお渡しするもの | 特にありません。 |
| 所要時間の目安 | 10分程度 |
| 注意事項 | 対象となる住宅 新築された日から10年以上を経過し、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(注釈1)の住宅で、下記のいずれかの人が居住するもの。 注釈1:併用住宅は、住居部分が全体の床面積の2分の1以上であること、貸家住宅は賃貸部分を除く。 ・65歳以上の高齢者 ・要介護認定または要支援認定者 ・障がい者認定を受けている方対象となる改修工事 次の工事を行ったもので改修工事費の(補助金等を除く)自己負担が50万円を超えるもの。 ・通路又は出入り口の拡幅 ・階段の勾配の緩和 ・浴室の改良 ・便所の改良 ・手すりの取付け ・床の段差の解消 ・出入り口の戸の改良 ・床面の滑り止めその他の減額措置との併用 ・省エネ改修に伴う減額措置との併用は可能です。 ・耐震改修に伴う減額措置、長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る減額措置との併用はできません。 ・バリアフリー改修に伴う減額措置は、同一家屋につき1回のみです。 |
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書(PDF:154KB)
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について(PDF:125KB)
財政部固定資産税課
電話0436-23-9812
耐震改修をした住宅に係る固定資産税の減額措置を受けたい
一定要件を満たした耐震改修を行った住宅については、工事完了後3か月以内に申告した場合、固定資産税を減額する措置です。
一定要件を満たした耐震改修を行った住宅については、工事完了後3か月以内に申告した場合、固定資産税の2分の1が減額されます。(1戸当たり住居部分の床面積120平方メートル相当分を限度とする。)
| 手続きの時期 | 改修工事完了後3か月以内。ただし、改修工事は平成18年1月1日から令和8年3月31日までに完了したものでなくてはなりません。 |
|---|---|
| 手続き可能な方 | 納税義務者 |
| 代理人による手続き | 可 |
| 手続き方法 | 耐震改修工事完了後3か月以内に固定資産税課窓口で申告してください。 (申告書については下部よりダウンロード可) |
| 必要書類 | 住宅の耐震改修に伴う固定資産税減額申告書住宅耐震改修証明書又は増改築等工事証明書若しくは住宅性能評価書(耐震等級に係る評価が等級1から3のもの) (1)住宅耐震改修証明書の発行主体 ・市原市都市部建築指導課 (2)増改築等工事証明書の発行主体 ・建築事務所に属する建築士、指定確認検査機関、 登録住宅性能評価機関 (3)住宅性能評価書の発行主体 ・登録住宅性能評価機関耐震改修に要した費用を証する書類(領収証等)長期優良住宅認定通知書の写し(認定長期優良住宅に該当することとなった住宅のみ。ただし、既に減額の適用を受けたことがある場合を除く。) |
| その他お持ちいただくもの | 特にありません。 |
| 手続きにかかる費用 | 無料です。 |
| 手続き後にお渡しするもの | 特にありません。 |
| 所要時間の目安 | 10分程度 |
| 注意事項 | 対象となる住宅 耐震改修をした住宅で、以下のすべての要件を満たすもの ・昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること。 ・平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に、費用が1戸当たり50万円を超える耐震改修工事が行われた住宅であること。 ・建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書(住宅耐震改修証明書又は増改築等工事証明書若しくは住宅性能評価書)があること。固定資産税の減額期間は、耐震工事完了時期により異なりますので、詳細は「住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について」をご覧ください。その他の減額措置との併用 ・バリアフリー改修に伴う減額措置、省エネ改修に伴う減額措置、長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る減額措置との併用はできません。 |
住宅の耐震改修に伴う固定資産税減額申告書(PDF:124KB)
耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書です。
住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について(PDF:120KB)
耐震改修に伴う固定資産税の減額措置についての説明です。
財政部固定資産税課
電話0436-23-9812
いちはら移住・定住促進応援事業
市原市では、皆様が住みやすく、安心して生活を送っていただけるよう、各種の支援制度をご用意しています。市原市での居住の際にはぜひご利用ください。(いちはら結婚新生活応援事業、いちはら三世代ファミリー定住応援事業、空き家バンク制度、空き家バンク事業(リフォーム等補助))
市原市では、皆様が住みやすく、安心して生活を送っていただけるよう、各種の支援制度をご用意しています。
市原市での居住の際にはぜひご利用ください。
移住・定住をお考えの方へ
「利用できる補助制度はあるのかな?」「どの補助制度を使えるのかわからない・・・」
以下から該当する支援制度をご確認ください。
お知らせ
いちはら結婚新生活応援事業(賃貸・引っ越し等の補助)をご利用いただいた方でも、いちはら三世代ファミリー応援事業をご利用いただけます!
いちはら結婚新生活応援事業(住宅購入補助利用者を除く)をご利用いただいた方でも、いちはら三世代ファミリー応援事業の補助対象要件に当てはまる方は、ご利用いただけます。市内にお住まいの親世帯の近くで、住宅を取得をされた方は、ぜひご利用ください。
各事業のご案内
いちはら結婚新生活応援事業
若者が安心して暮らせるまちへ向けて、結婚して新生活をスタートさせたいという若者を応援する、新たな制度を令和元年10月1日から開始しました。
若者が結婚を機に市内に定住するとき、新生活に必要となる住居費や引っ越し費用の一部を補助します。
いちはら三世代ファミリー定住応援事業
子育て世帯が安心して暮らせるまちへ向けて、親世帯の近くで家族で支え合って暮らしたいという子育て世帯を応援する、新たな制度を令和元年10月1日から開始しました。
子育て世帯が、親世帯の近くで住宅を取得するとき、その親世代が市内定住の場合に住宅取得の一部を補助します。
空き家バンク制度
不動産業者に仲介を依頼していない市原市内の空き家を貸したい、あるいは売りたい所有者の方が、物件を市に登録し、市がホームページ上でその物件情報を、市原市内に移住や定住を希望している方や市内在住の方に提供します。市が所有者とその物件を利用する希望者とのマッチングを行い、その後の実際の交渉を当事者間、あるいは宅建業者の仲介で行うことにより(この場合は、所定の仲介手数料がかかります)、市内の空き家の有効活用を図る制度です。
空き家バンク事業(リフォーム等補助)令和4年4月開始!
空き家バンクに登録されている物件を購入して居住するとき、物件のリフォーム等工事費用、地域資源「ゴルフ」「アート」「里山(農業関連)」の施設整備費用の一部を補助します。
都市部住宅政策課
電話0436-23-9841
市原市の空き家対策総合ページ
市原市が実施する空き家対策全般(空家の除却費や改修費の一部を補助)についてまとめたウェブページです。【具体的な事業内容等については、住宅政策課窓口での相談をお願いします。】
1 空き家の定義
国では、「1年以上住んでいない、または使われていない建物」を「空き家」として定義しています(下記参照)。ただし、「空き家」といっても、さまざまな「空き家」があります。いずれの空き家も所有者の財産であり、適切に管理する義務があります。
【空き家の一例】
・管理された「空き家」 (すぐにでも使用できる状態)
・経年劣化相当の「空き家」 (建物などに若干の傷みはあるものの、周辺に支障がない状態)
・著しく状態の悪い「空き家」 (建物などに著しい傷みがあり、周辺に支障がある状態)
【法令等の定義】
「空家等対策の推進に関する特別措置法」及び「市原市空家等の適正な管理に関する条例」の「空き家の定義」は、次のとおり定められています。
【空家等対策の推進に関する特別措置法】
使用実績のない期間が1年以上の建築物(建物本体、門・塀など)またはこれに附属する工作物(看板・擁壁など)及びその敷地(立木その他の土地に定着するもの含む)をいいます(空家法第2条第1項を参照)。
空家等対策の推進に関する特別措置法(国土交通省ウェブサイトへ)
【市原市空家等の適正な管理に関する条例】
空家法では対象とならない、以下の①または②を対象としています(空家条例第2条第1項第2号を参照)。
① 区分所有権を有する長屋の空き室(例:長屋住宅やテラスハウスの空き室など)
(空家法では、全室が空き室でなければ対象になりません。)
② 使用実績のない期間が1年未満の空き家
市原市空家等の適正な管理に関する条例(市原市ウェブサイトへ)
2 空き家の予防などのポイント
空き家の予防・管理・活用等について
周辺環境に悪影響を与えるような空き家とならないよう、事前の「予防」や適切な「管理」、またはリフォームや売却も含めた「活用」などの対策をすることが重要です。
【建物所有者へのポイント】
空き家の予防:空き家になる前に、建物を誰にどう引き継ぐか、今から決めておきましょう!
ステップ1:現在の登記を確認しましょう。
ステップ2:生前に相続対策について話し合いましょう。
ステップ3:司法書士などの専門家に相談しましょう。
空き家の管理:空き家を財産として受け継いでいくために定期的に管理をしましょう!
ポイント1:定期的に建物の状態を点検しましょう。
ポイント2:不良箇所を発見した場合は早めに対応しましょう。
空き家の活用:自分に合った活用方法を検討しましょう!
ケース1:所有者自身で活用しましょう。
ケース2:賃貸・売却して活用しましょう。
ケース3:解体しましょう。
空き家対策の出前講座(おでかけくん)について
空き家になる前の段階から、空き家問題への興味関心を持っていただくために、町会等の団体を対象とした出前講座を実施しています。
講座の内容は、市が実施する空家等対策の概要や、空家になる前にできる対策を、市職員が地域の集会施設等にお邪魔して、分かりやすく説明します。
出前講座の申し込み方法等については、以下のページをご確認ください。
3 空き家バンク制度
空き家バンク制度の詳細については、次のリンクをクリックしてください。
4 空き家に関する本市の支援制度
(1) 空家等除却・活用提案モデル事業(除却費用に対して最大50万円補助、改修費用に対して最大100万円補助)
町会などの地域の皆様が主体となって空き家を利活用することで、地域の課題解決へ取り組むモデル事業について、空き家の除却費や改修費の一部を補助します。
【主な補助内容(その他詳細な条件がありますので、次の事業ページを確認してください)】
① 補助対象者:空き家を所有または賃貸する次のいずれかの者
ア 町会や自治会などの自治組織 イ 事業の実施にあたり自治組織の協力が得られる団体や個人
② 対象物件:市内に所在する専用住宅又は併用住宅の空き家
③ 対象経費・補助率・上限額:[除却]対象物件の除却に係る経費・4/5・50万円
[活用]対象物件の活用に係る経費・2/3・100万円
(2) 狭小敷地等空家除却支援事業(除却費用に対して最大50万円補助)
隣接する空き家の敷地が無接道や狭小な敷地で、その敷地だけでは活用が困難なときに、隣接者が当該空き家を取得及び除却し、自己の土地と一体的に10年間利用するときに、除却費の一部を補助します。
【主な補助内容(その他詳細な条件がありますので、次の事業ページを確認してください)】
① 補助対象者:無接道や狭小な敷地に隣接する土地所有者
② 対象物件:無接道や狭小な敷地に建っている空き家
③ 対象経費・補助率・上限額:除却工事に係る経費・4/5・50万円
(3) 空き家バンク事業(リフォーム等補助)補助金(改修費用に対して最大100万円補助)
空き家バンクで購入された空き家を対象に、リフォームなどの費用の一部を補助します。
【主な補助内容(その他詳細な条件がありますので、以下の事業ページを確認してください)】
① 補助対象者:空き家バンク物件を購入した者
② 対象物件:購入した空き家バンク物件
③ 対象経費・補助率・上限額:改修工事に係る経費・1/3・100万円
5 空き家のリスク
空き家をそのままにしておくと…
空き家を適切に管理せずに放置すると、建物の劣化が進み、防災・防犯・衛生面などの問題が発生する恐れがあります。空き家が、適切に管理されていないことにより、他人に損害を与えた場合、所有者は民法上の損害賠償責任を負う可能性があります。
本市でも、台風などの強風時に屋根が飛んでしまい、隣接の建物に被害が発生したケースがあります。
また、建物の劣化状況により、法令等の規定により「特定空家等」と認定され、勧告を受けたときは、固定資産税の住宅用地特例の対象から除外されます。
空き家の相談
住宅政策課では、周辺環境に支障のある空き家に関する相談について、次の対応を行っています。
① 空き家の状況確認
② 所有者調査
③ 現場写真を含めた管理依頼文書の送付
周辺の空き家でお困りの方は、電話又は次の相談フォームで相談してください。
都市部住宅政策課
電話0436-23-9841
木造住宅の耐震診断を受けたい
木造住宅無料耐震相談会にご参加いただき、「耐震性がない」と判断された場合
市が認定した耐震診断士がご自宅に伺い、より詳しい耐震診断(精密診断)を受けることができます。
耐震診断の内容
市が認定した耐震診断士がご自宅に伺います。
以下の点を調査することで、ご自宅の地震に対する強さを診断します。
・周辺状況の確認
・簡易地盤調査
・建物外部・基礎の劣化確認
・内部劣化・傾斜確認
・筋交い位置の調査
・既存図面と現地の変更点の確認
※調査は原則「非破壊調査」です。
内部については、天井・床の点検口より目視確認をします。
建物によっては全体確認ができない場合があります。
耐震診断の結果
耐震診断の結果では、現況の耐震性に加え、以下の内容をご提案します。
・補強工事の内容(案)や、工事費用(概算)
・耐震改修工事に対する補助金額(概算)
対象者
以下の全てに該当する方
・市で開催する木造住宅無料耐震相談会に参加された方、もしくは専用ソフトを用いて簡易な耐震診断を受けている方
・「対象となる建築物」の所有者で、自らが居住または居住予定の方
対象となる建築物
平成12年5月31日以前に建てられた木造(在来軸組工法)2階建て以下の住宅
※在来軸組工法とは・・・基礎、柱、はり等の部材を用いて建てられる工法
以下のような住宅は、対象外です。
【用途的に対象にならない場合】
・テラスハウスやアパートなどの共同住宅である。
・店舗など住居用途以外に使用している面積が全体の1/2以上ある。
【構造的に対象にならない場合】
・ツーバイフォー工法、丸太工法、メーカー独自の工法等で建てられている場合。
・鉄筋コンクリート造、鉄骨造等木造以外の部分がある場合。
・スキップフロア(中二階)がある場合
以上の構造(工法)で建てられた住宅は、この事業では診断できません。
申し訳ありませんが、施工されたメーカー等にご相談ください。
診断費用(申請者負担)
5,000円(診断費用73,000円のうち、68,000円は市が補助)
お申し込みについて
建築指導課 耐震化推進係へお電話ください(TEL:0436-23-9091)
お申し込み方法や、事業の流れをご説明します。
注意点
・調査から結果が得られるまで、1~2ヶ月程度かかります。
・事前に、市で開催する木造住宅無料耐震相談会に参加、もしくは専用ソフトを用いて簡易な耐震診断を受けている必要があります。
都市部建築指導課
電話0436-23-9091
木造住宅の耐震工事の補助金を受けたい
補強を必要とする木造住宅の耐震性能向上を図る工事に対し、その経費の一部を補助する事業です。
市では、耐震診断の結果、耐震補強が必要とされる木造住宅の耐震性を向上させる改修工事に対して、最大115万円の補助を行っています。
残念ながら、地震を防ぐことはできませんが、必要なのは、大地震が起きても、倒壊することなく、外に逃げる時間を確保できる、そんな住まいづくりをしていくことです。
大切な財産やご家族の命を守るため、ぜひ耐震改修工事をご検討ください。
対象となる建築物
以下の全てに該当する住宅
・平成12年5月31日以前に建てられた住宅
・木造(在来軸組工法)で建てられた2階建て以下の住宅
・市原市木造住宅耐震診断事業において、倒壊の危険性が認められた住宅
・申請者が、耐震改修工事後、自ら居住する予定の住宅
補助金額(補助率)
耐震改修工事費用の最大8割(上限115万円)
※現状の耐震性や、住宅の面積等によって補助金額は変わります。
耐震設計から耐震改修工事までの流れ
耐震設計(事前協議)について
耐震診断後、耐震改修工事に進むための準備として、耐震設計(事前協議)を行います。
条件(注意点)は以下のとおりです。
・市に登録された耐震設計監理者により設計されること。
・耐震設計の内容が、市が認定した評価員により、適正な改修計画として評価されること。
耐震改修工事について
事前協議が完了後、工事に進むことができます。
条件(注意点)は以下のとおりです。
・市に登録された耐震設計監理者により工事監理され、市に登録された改修事業者により施工されること。
・工事完了後、市が認定した評価員により、所定の耐震性能を有するとして評価されること。
市に登録された耐震設計監理者・改修事業者を選ぶ
補助制度受けるためには、以下の名簿から耐震設計監理者(設計者)、改修事業者(工務店)をお選びいただき、直接、耐震設計監理者へご連絡ください。
市原市耐震改修設計監理者、事業者等登録名簿(令和7年6月4日更新)
「代理受領制度」を利用し、当初の費用負担を軽減
工事業者等が、所有者(申請者)に代わり、市から補助金を受け取る制度です。
所有者(申請者)は、工事費用から補助金額を差し引いた金額のみを支払うため、当初の持ち出し費用が軽減されます。
都市部建築指導課
電話0436-23-9091
特定既存耐震不適格建築物等の耐震診断補助事業(町会施設などの耐震診断)
防災上重要な建築物や多数の方が利用する建築物の耐震診断に要する経費の一部を補助する事業です。
災害に強いまちづくりを促進するために、防災上重要な建築物(病院、学校等)や多数の人が利用する建築物(町会施設、共同住宅、店舗等)の耐震診断を行う場合にかかる費用に対し、補助を行っています。
補助対象者
・補助対象建築物の所有者等(所有者若しくは区分所有者の団体の管理者又は管理組合法人の理事)で、市町村税を完納している者
・集会施設の設置及び管理する町会
・地震により緊急輸送道路等の通行の妨げとなる通行障害既存耐震不適格建築物の所有者等
補助対象建築物
昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた民間建築物で以下のいずれかに該当するもの
(1)多数の者が利用する一定規模以上の建築物
(2)災害時に利用を確保する必要のある建築物(要安全確認計画記載建築物)
「千葉県耐震改修促進計画」又は「市原市耐震改修促進計画」で定められた大規模な地震が発生した場合において、その利用を確保することが公益上必要な建築物です。
(3)災害時に道路閉塞させる建築物(通行障害既存耐震不適格建築物)
<災害時に道路閉塞させる建築物詳細図>
道路と建物の高さが重要となります。前面道路が12メートルを超える場合、幅員の2分の1を超える建築物か、前面道路が12メートル以下の場合高さが6メートルを超える建築物が対象となります。
※上記の道路とは、「千葉県耐震改修促進計画」又は「市原市耐震改修促進計画」に記載されたものです。
(4)階数が3以上で、かつ、床面積の合計が1000平方メートル以上の分譲マンション
(5)町会集会施設
(6)災害時、安全性を緊急に確かめる必要がある大規模な建築物(要緊急安全確認大規模建築物)
耐震改修促進法附則第3条で定める建築物です。
(7)その他市長が地震による倒壊を防ぐため、耐震診断をすることが特に必要と認めた建築物
補助金額(補助率)
耐震診断等にかかる費用の3分の2の額(上限60万円)
対象となる事業(耐震診断等)
補助対象建築物に対して行う耐震診断及び当該耐震診断を行うための試験(部材の強度試験、公的機関の判定)等とします。
実際に耐震診断を行う者は、建築士(一級、二級または木造)の資格を有し、建築物の構造に応じた耐震診断講習会の修了者(耐震診断事業者)とします。
耐震診断等を請け負うことができる耐震診断事業者
耐震診断は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)の別添第1の指針に基づいて行うものに限ります。
耐震診断事業者が請負うことが出来る補助対象建築物は、建築士法第3条、第3条の2、第3条の3で規定される「一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければできない設計又は工事監理」の用途や規模と同様とします。
例えば、補助対象建築物用途規模が病院(階数3階以上、かつ、床面積の合計が1000平方メートル以上)の場合、耐震診断事業者は、一級建築士となります。二級建築士や木造建築士では要件を満たせません。
注意点
補助金の交付決定を受けずに、耐震診断等の事業を行った場合は、補助金を受けられません。
必ず、事前に建築指導課へご相談ください。
「代理受領制度」を利用し、当初の費用負担を軽減
工事業者等が、所有者(申請者)に代わり、市から補助金を受け取る制度です。
所有者(申請者)は、工事費用から補助金額を差し引いた金額のみを支払うため、当初の持ち出し費用が軽減されます。
都市部建築指導課
電話0436-23-9091
耐震シェルター等設置補助事業のご案内
地震による木造住宅の倒壊から市民の生命を守るため、耐震シェルター及び防災ベッドの設置費用の一部を補助する事業です。
耐震シェルターとは、建物の内部に設置あるいは部分的に補強することで、地震によって建物が倒壊しても、命を守ることができる装置です。
この耐震シェルター等を設置する費用の一部を補助します。
対象者
・市の補助金を受けて耐震改修工事等を行っていない方
・以下の「対象となる建築物」を所有し、自らが居住または居住予定の方
対象となる建築物
市で行った耐震診断(精密診断)の結果、「耐震性がない」と判断された木造住宅
補助金額(補助率)
耐震シェルター等の設置に係る費用の2分の1(最大25万円)
補助の対象となる耐震シェルター等
補助事業パンフレットをご覧ください。
詳しい費用等については、各メーカーへお問い合わせください。
申込方法
建築指導課 耐震化推進係へお電話ください(TEL:0436-23-9091)
注意点
市で行った耐震診断(精密診断)の結果、耐震性がない(評点1未満)ことの結果を受けている必要があります。
「代理受領制度」を利用し、当初の費用負担を軽減
工事業者等が、所有者(申請者)に代わり、市から補助金を受け取る制度です。
所有者(申請者)は、工事費用から補助金額を差し引いた金額のみを支払うため、当初の持ち出し費用が軽減されます。
危険ブロック塀等の安全対策事業のご案内
指定通学路に面して設置された倒壊等の危険があるブロック塀等(危険ブロック塀等)の撤去を進めるため、予算の範囲内で費用の一部を補助する事業です。
街の身近にあるブロック塀。プライバシーの確保や、火災などから、わたしたちの生活を守るために役立っています。
しかし、きちんと施工されていない場合や、老朽化している場合に、地震などにより、倒壊してしまうと、通行人に怪我を負わせたり、緊急車両の通行の妨げになったりする場合があります。
市では、小中学校の指定通学路に面した倒壊等の危険性があるブロック塀等について、撤去する費用の補助を行っています。
危険ブロック塀等とは
市内にある高さ1mを超えるコンクリートブロック造、石造、レンガ造、これらに類する構造の塀、門柱及びこれらの基礎、並びにコンクリートや間知石等からなる擁壁
指定通学路とは
・小中学校の児童や生徒が通学のために通行する道路の区間で、特に安全を確保する必要があるとして定められた通学路(交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令(昭和41年政令第103号)第4条)
・市原市通学路事故防止対策協議会が承認した通学路
補助対象者
市内にある危険ブロック塀等の所有者等
※自ら工事しようとする場合や、土地の売買を目的としている場合は、補助が受けられません。
補助金額(補助率)
危険ブロック塀等撤去の補助
次の(1)(2)のいずれか少ない方の額(上限30万円)
(1)撤去するブロック塀等の長さ(m)×12,000円
(2)実際の工事費
撤去後のフェンス新設の補助
次の(1)(2)のいずれか少ない方の額(上限15万円)
(1)新設するフェンスの長さ(m)×10,900円
(2)実際の工事費
補助金を申請するまでの流れ
・まずは、事前相談です。建築指導課に、電話か窓口にて、ご相談ください。
・職員が現地に伺い、「倒壊等の危険があるかどうか」の調査を行います。
※安全性を判断するものではありません。ブロック塀等の耐震診断をご希望される場合は、専門家へご相談ください。
・後日、市から「補助の対象となり得るかどうか」のご連絡を差し上げます。
・必要書類(見積書の写し、図面等)を添えて、申請書類を提出してください。
注意点
・補助金の申請手続きの前に工事に着手(契約を含む)した場合は、補助金が受けられません。
・工事を完了し、当該年度の1月末日までに完了実績報告を提出してください。期日が過ぎた場合は、補助金が受けられません 。
・補助金交付決定後、申請内容に変更が生じた場合や工事を中止する場合には、計画の変更又は中止の手続きが必要となります。
「代理受領制度」を利用し、当初の費用負担を軽減
工事業者等が、所有者(申請者)に代わり、市から補助金を受け取る制度です。
所有者(申請者)は、工事費用から補助金額を差し引いた金額のみを支払うため、当初の持ち出し費用が軽減されます。
ブロック塀等撤去の関連事業
生垣設置奨励補助
緑化推進とブロック塀の倒壊防止のため、住宅用地の既存のブロック塀の撤去費用と生垣を新設するための費用を補助します。
狭あい道路後退用地整備事業
全面の道路幅員が4メートルに満たない『狭あい道路』を拡幅整備するため、道路に接する用地内にある工作物(門柱・塀・擁壁・生垣等)を撤去する費用を補助します。
都市部建築指導課
電話0436-23-9091
瓦屋根の全面改修に対する補助のご案内(瓦屋根耐風改修促進事業)
令和元年房総半島台風を受け、建築基準法の告示が改正され、瓦屋根の緊結方法が強化されました。本市においては、既存建築物の瓦屋根についても、改修を促進するため、瓦屋根の全面改修に対する補助を行います。補助制度を利用する場合、まずは電話で事前相談の申し込みが必要です。
令和元年に発生した台風15号では、多くの家屋の瓦屋根が飛散しました。
これを受け、建築基準法の告示が改正され、瓦屋根の緊結方法が強化されました。
市では、既存建築物の瓦屋根について、全面的に葺き替える場合に補助を行っています。
対象・条件
・自己所有の建築物の瓦屋根(粘土瓦またはセメント瓦)で、現行基準に適合していないもの。
・一棟の建築物の瓦屋根を全面的に葺き替えること。
・他の改修工事の補助制度等により、二重に補助金を受けていないもの。
現行基準に適合しない瓦屋根とは
・令和2年国土交通省告示第1435号により改正された昭和46年建設省告示第109号に適合していない瓦屋根のことをいいます。
補助金額(補助率)
次の(1)(2)のいずれか少ない方の額(上限55万2千円)
(1)瓦屋根の葺き替え工事にかかる費用×23%
(2)対象となる瓦屋根の面積(㎡)×24,000円×23%
補助金を申請するまでの流れ
・まずは、事前相談です。電話か窓口にて、ご相談ください。
・職員がご自宅へ伺い、見上げてわかる範囲で、瓦屋根の状況を確認します。
・有資格者による調査を行い、現行基準に適合していないことを確認してください。
※有資格者
「建築士(一級、二級または木造)」、「瓦屋根診断技士」、「瓦屋根工事技士」、「かわらぶき技能士」いずれかの資格をもつ者のことです。
・必要書類(見積書の写し、図面等)を添付し、建築指導課へ、提出してください。
注意点
・補助金交付決定の前に葺き替え工事に着手(契約を含む)した場合は、補助金が受けられません。
・工事を完了し、当該年度の1月末日までに完了実績報告を提出してください。期日が過ぎた場合は、補助金が受けられません 。
・補助金交付決定後、申請内容に変更が生じた場合や工事を中止する場合には、計画の変更又は中止の手続きが必要となります。
「代理受領制度」を利用し、当初の費用負担を軽減
工事業者等が、所有者(申請者)に代わり、市から補助金を受け取る制度です。
所有者(申請者)は、工事費用から補助金額を差し引いた金額のみを支払うため、当初の持ち出し費用が軽減されます。
各種ダウンロード
関連資料
都市部建築指導課
電話0436-23-9091
当てはまる項目はありましたか?
瓦屋根の全面改修に対する補助のご案内(瓦屋根耐風改修促進事業)
こちらは弊社でお力になれますので、是非お気軽にご相談くださいませ!
外壁塗装以外にできる事を記載しております。